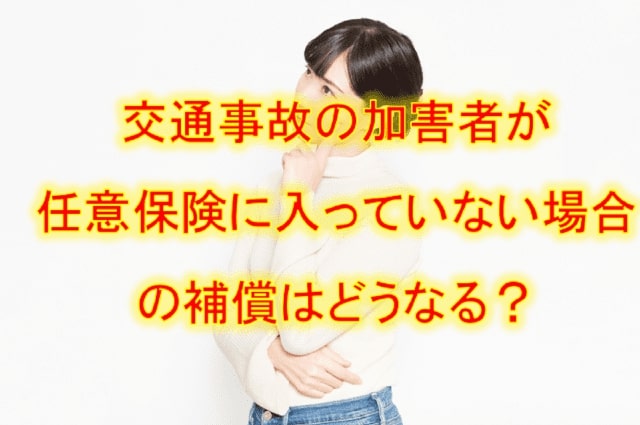
交通事故で被害を受けたら、通常は加害者側の任意保険会社から損害賠償金を受け取ることができます。しかし、加害者が任意保険に入っていないことも珍しくはありません。
そんなとき、被害者の方は「補償はどうなるのだろうか」「治療費は自分で支払わなければならないのか」と不安になることでしょう。
しかし、交通事故の加害者が任意保険に入っていない場合でも、被害者は治療費や慰謝料などの補償を受ける事が出来ます。
交通事故の加害者が任意保険に入っていない場合に補償を受ける方法
加害者が任意保険に入っていない場合に被害者が補償を受けるには、以下の方法があります。
・自分の任意保険を利用する
・加害者の自賠責保険に請求する
・加害者本人やその責任者に請求する
・政府補償事業に申請する
・業務中の事故は労災保険が使える
・健康保険を使って治療を受ける
以下で、順に解説していきます。
自分の任意保険を利用する
加害者側から十分な賠償を受けられない場合、被害者の方が任意保険に加入していればその保険を利用することができます。
交通事故の加害者が任意保険に入っていない場合に利用できる主な保険は、次の2つです。
・人身傷害保険
・車両保険
人身傷害保険
人身傷害保険とは、交通事故で任意保険の契約者側がケガをした場合の人身損害を補償してもらえる保険のことです。治療費だけでなく慰謝料や休業損害、その他にも後遺障害や死亡に関する損害賠償金も支払われます。
交通事故の際、自分の方が過失が多い場合でも損害分の補償が受けられます。
人身傷害保険を利用しても保険の等級には影響がないので、安心して利用することができます。
ただし、契約内容によって賠償額に上限があるため、重傷を負った場合には十分な補償を受けられない可能性があります。
また、人身傷害保険に加入していない場合や、加入していても十分な補償が受けられない場合もあります。
その他、搭乗者傷害保険や無保険車傷害保険など、ある程度似たような補償が受けられる保険もあります。
まずはご自身の契約内容をご確認の上、保険会社に問い合わせてみましょう。
車両保険
車両保険とは、自分の車にかける保険のことです。交通事故や災害時、車両の修理代や買い換え費用、レッカー代などが補償されます。
一般的な車対車の事故の場合はほとんどのケースで車両保険を利用できますが、当て逃げなど特殊なケースでは契約内容によっては利用できないこともあります。また、契約内容によって一定の自己負担額が生じることにもあります。
車両保険を利用すると保険等級が下がり、翌年以降の保険料が上がる可能性があることにも注意が必要です。
加害者の自賠責保険に請求する
加害者が任意保険に入っていなくても、自賠責保険には入っています。自賠責保険は強制加入保険であり、加入しなければ車検を通過することができないからです。
交通事故の被害者は、加害者側の自賠責保険に対して、補償を請求することができます。
ただし、自賠責保険は人身事故の被害者に対する最低限の補償を目的とした保険なので、補償額は任意保険よりも低くなります。また、対人補償に限られているため車など物に対する補償はありません。
損害の種類に応じて支払限度額が以下のように定められています。
| 損害の種類 | 支払限度額 |
| 傷害 | 120万円 |
| 後遺障害 | 後遺障害等級に応じて75万円~4,000万円 |
| 死亡 | 3,000万円 |
| 物損 | 適用なし |
車の破損や、この限度額を超える損害を受けた場合は、超える部分について加害者本人やその責任者へ補償を請求することになります。
加害者本人やその責任者に請求する
当然ですが、交通事故の被害者は加害者に対して直接、損害賠償請求を行うことができます。
ただ、加害者本人との話し合いでは筋の通らない主張に終始されたり、お互いが感情的になるなどして交渉が難航することもよくあります。そのため、裁判が必要になるケースが多くなっています。
さらに、任意保険に加入していない場合、多くの加害者は損害賠償金の支払い能力がないケースが多々あります。
なお、以下の場合には、加害者本人だけでなく、その責任者に対して損害賠償請求を行うことも可能です。
| 責任者 | 損害賠償請求できる場合 |
| 加害者の保護者(両親など) | ・保護者が加害車両の所有名義人であり、自賠法上の運行供用者にあたるとき ・加害者が未成年で、保護者の監督義務違反によって事故が発生したとき |
| 加害者の勤務先会社や雇い主 | ・加害者が仕事で車を運転して交通事故を起こしたとき |
加害者側が誠意をもって対応してくれればよいですが、交渉が難航する場合は弁護士などの専門家に相談して示談交渉を進める方がよいでしょう。
政府補償事業に申請する
加害者が自賠責保険にも加入していない場合や、ひき逃げなどで加害者不明の場合は、政府補償事業に申請することで補償を受けることができます。
政府補償事業とは、これらの場合に政府(国土交通省)が加害者に代わって被害者に対する補償を行う制度のことです。
補償内容は自賠責保険と同様なので不足する場合も多いですが、最低限の補償は受けられます。
申請は保険会社を通じて行います。申請を受け付けている保険会社や必要書類などについては、こちらの国土交通省のページで紹介されていますのでご参照ください。
参考:国土交通省|自動車総合安全情報
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html
業務中の事故は労災保険が使える
ご自身が仕事中または通勤中に交通事故に遭った場合には、労災保険から補償を受ける事が出来ます。
労災保険が適用されると治療費は全額、労災から支払われます。労災の認定を受けるまでの治療費はいったん窓口で支払う必要がある場合もありますが、その分も後日、労災保険から支給されます。
また、休業補償を受け取ることもできます。補償額は、休業4日目から1日あたり給料の80%です。
労災保険は自賠責保険と異なり支払限度額はないので、該当する場合は積極的に利用するとよいでしょう。
健康保険を使って治療を受ける
交通事故によるケガの治療でも健康保険を使うことは出来ます。健康保険を使うには、ご自身が加入している健康保険組合などへ「第三者行為による傷病届」という書類を提出し承諾を得る必要があります。
第三者行為、つまり、加害者のいるケガでは、本来その治療費は加害者が負担すべきものです。健康保険組合は被害者のために治療費を一時的に建て替え、のちに加害者(加害者の健康保険組合)に請求する流れになっています。
健康保険を使った場合でも治療費の一部(通常3割)は自己負担しなければなりませんが、その分は後に加害者本人やその責任者へ請求できます。その際には証拠が必要となるので、領収証や診療報酬明細書、診断書などを保管しておきましょう。
仕事を一定期間休んだ場合には健康保険から傷病手当金を受け取ることもできるので、こちらも申請するとよいでしょう。
損害賠償請求権の時効に注意しよう
損害賠償請求権には時効があります。任意保険を使う場合には、保険会社が対応してくれるのであまり心配はいりません。しかし、ご自身で自賠責保険、加害者本人やその責任者へ請求する場合には、時効が完成する前に請求しなければなりません。
交通事故による損害賠償請求権の時効期間は、以下のようになっています。
| 請求権の種類 | 時効期間(2017年3月31日以前に発生した事故) | 時効期間(2017年4月1日以降に発生した事故) |
| 傷害に関する請求権 | 事故の翌日から3年 | 事故の翌日から5年 |
| 後遺障害に関する請求権 | 症状固定の翌日から3年 | 症状固定の翌日から5年 |
| 死亡に関する請求権 | 事故の翌日から3年 | 事故の翌日から5年 |
| 物損に関する請求権 | 事故の翌日から3年 | 事故の翌日から3年 |
| 保険会社に対する保険金請求権 | 事故の翌日から3年 | 事故の翌日から3年 |
改正民法が2020年4月1日に施行されたことにより、人身損害に関する損害賠償請求権の時効期間は3年から5年に伸長されています。
ただし、これは加害者本人やその責任者に対して損害賠償請求を行う場合に限られます。保険会社に対する保険金の請求権の時効期間は、自賠法により3年のままなのでご注意ください。
まとめ
交通事故の加害者が任意保険に入っていない場合でも、ご自身の任意保険を使うことで十分な補償が受けられます。
その他の場合は一定の補償を受けることができたとしても十分な補償が受けられない可能性が高くなるようです。
交通事故に遭ってしまったら、お金の心配が出てしまうかもしれませんが、後遺症を残さないためにもまずは治療を受ける事を優先させてください。
不安や心配などがある場合や、どうすればよいのか分からない場合には、ひとりで悩まず弁護士に相談することも出来ます。
鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故に詳しい弁護士を紹介しています。
「いきなり弁護士なんて!」と躊躇される方は当院で簡単なご相談なら受け付けていますのでお声がけください。
