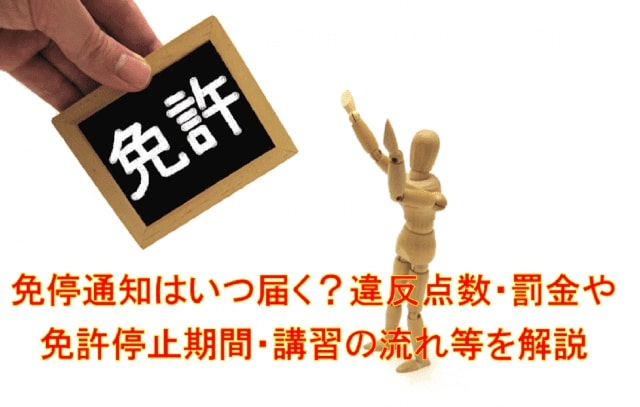
交通事故を起こすと免許に違反点数が付き、一定の点数がたまると免許停止や免許取消しといった行政処分を受けることがあります。
免許停止の対象となった場合でも、指定された講習を受ければ停止処分を免除されたり、停止期間が短縮される場合もあります。
この記事では、交通事故を起こした場合に付加される違反点数や罰金の相場、免許停止・免許取消しの期間、講習の流れ等を解説していきます。
交通事故を起こしたときの行政処分『点数制度』とは?
行政処分とは、都道府県公安委員会が道路交通法に基づき行う免許停止や免許取消し等の処分のことです。
免許停止や免許取消しの処分の対象となる基準は、違反点数よって定められています。交通違反や交通事故の内容に応じて所定の点数が付加され、過去3年間の累積点数等に応じて行政処分の内容が決まります。この制度のことを『点数制度』といいます。
『刑事処分』と『行政処分』の違い
刑事処分とは?
刑罰法規に違反した場合には刑事事件の対象となり、刑事罰としての罰金等を科せられることを『刑事処分』と言いいます。
交通事故を起こしたときは、道路交通法等の法令に対し法令違反を行っている可能性があり、人身事故を起こした場合には、自動車運転処罰法等の法令に対し違反が認められると刑事事件として刑事処分を受ける事になります。
行政処分とは?
行政処分とは、今後の道路交通上の危険を防止するという目的で刑事処分とは別に課せられるものです。行政処分を受けても前科は付きません。
なお、一定の軽微な違反行為に対しては『反則金』という行政罰が課せられることがあります。反則金とは、いわゆる『青切符』によって納付が命じられるものです。
刑罰法規に違反するものの軽微な交通違反行為については、反則金を納めれば刑事罰は免除されます。青切符を受け取ったにもかかわらず反則金を納めなければ、原則に戻って刑事事件の対象となり、刑事罰としての罰金等が科せられる可能性があります。
付加点数とは?
運転免許の違反行為は『点数加算』によって管理されています。
交通違反や交通事故で加算される点数には、大きく分けて次の2種類のものがあります。
- 基礎点数…違反行為に対して加算される点数(一時停止無視など)
- 付加点数…交通事故を起こした場合等に付加される点数
人身事故は人の死傷という重大な結果を引き起こす危険なものですので、人身事故を起こした場合には基礎点数に加えて付加点数も付けられることになります。
物損事故では原則として付加点数は付かない
一方、物損のみの事故の場合は、原則として付加点数は付きません。
過失で物を壊す行為は刑罰法規には触れないため、警察では無事故と同じ扱いとなるのです。
ただし、事故を起こした際に違反行為があれば基礎点数が付くことはありますし、当て逃げをした場合には付加点数が付きます。
交通事故で付加される違反点数の一覧
交通事故を起こしたときに付加される違反点数について、基礎点数と付加点数とに分けてご紹介します。
基礎点数
交通事故の原因となる違反行為にはさまざまなものがありますが、主な違反行為とそれに対する違反点数は以下のとおりです。

付加点数
人身事故を起こした場合の付加点数は、相手方が受けた被害の程度に応じて以下のとおり定められています。
| 被害の程度 | 専ら加害者の不注 意による場合 | 左記以外の場合 |
| 死亡事故 | 20点 | 13点 |
| 傷害事故 ※治療期間3ヶ月以上または後遺障害あり | 13点 | 9点 |
| 傷害事故 ※治療期間30日以上3ヶ月未満 | 9点 | 6点 |
| 傷害事故 ※治療期間15日以上30日未満 | 6点 | 4点 |
| 傷害事故(治療期間15日未満) または建造物損壊事故 | 3点 | 2点 |
例⦆安全運転義務違反によって人身事故を起こし、被害者が全治1ヶ月の負傷をした場合
加害者の過失が原因
・基礎点数2点+付加点数9点=違反点数11点
なお、以下のような悪質な行為があった場合には、さらに点数が加算されます。
- ひき逃げ…35点
- 当て逃げ…5点
- 危険運転致死傷等の特定違反行為…35~62点
交通事故の加害者に科せられる罰金の相場
人身事故の加害者は通常、自動車運転処罰法の『過失運転致死傷罪』として刑事罰の対象となります。刑罰の上限は、7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金です。
ただし、死亡事故を起こした場合や前科がある場合、事故・違反歴が多い場合でもない限り、実際に処罰されることは多くありません。処罰されるとしても、略式命令(書類のみで行われる裁判)により10~50万円程度の罰金となるのが相場的です。
なお、『反則金』の金額は以下のとおり違反点数に応じて定められています。

違反点数がたまると免許停止・免許取消しになる
累積の違反点数が一定の点数に達すると、免許停止や免許取消しの処分を受けてしまいます。
その点数や免停期間、欠格期間は以下のとおりです。
免許停止になる点数と停止期間
累積の違反点数が6点になると、免許停止処分の対象となります。
この場合の免許停止期間は30日です。
ただし、免許停止処分の対象となる点数や免停期間は、以下のように前歴(過去の行政処分歴)によっても異なります。
【前歴がない場合】
| 累積違反点数 | 免停期間 |
| 6点~8点 | 30日 |
| 9点~11点 | 60日 |
| 11点~14点 | 90日 |
【前歴が1回】
| 累積違反点数 | 免停期間 |
| 4点~5点 | 60日 |
| 6点~7点 | 90日 |
| 8点~9点 | 120日 |
【前歴が2回】
| 累積違反点数 | 免停期間 |
| 2点 | 90日 |
| 3点 | 120日 |
| 4点 | 150日 |
【前歴が3回】
| 累積違反点数 | 免停期間 |
| 2点 | 120日 |
| 3点 | 150日 |
免許取消しになる点数と欠格期間
累積の違反点数が15点になると、免許取消し処分の対象となります。
免許取消し処分には欠格期間というものがあり、その期間が経過するまでは新たに免許を取得することができません。
免許取消しになる点数と欠格期間は、以下のとおり前歴によって異なります。
| 前歴 欠格 期間 | なし | 1回 | 2回 | 3回 |
| 1年 | 15~24点 | 10~19点 | 5~14点 | 4~9点 |
| 2年 | 25~34点 | 20~29点 | 15~24点 | 10~19点 |
| 3年 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | 20~24点 |
| 4年 | 40~44点 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 |
| 5年 | 45点~ | 40点~ | 35点~ | 30点~ |
なお、危険運転致死傷など悪質な「特定違反行為」があった場合には、より厳しい処分を受けることがあります。
免許停止・免許取消しの通知はいつ届く?
通知が届くまでの期間は、1週間~1ヶ月程度です。
累積点数が上記の基準に達しても、自動的に免許停止や免許取消しとなるわけではなく、まずは公安委員会から通知が届きます。
この通知書には事情聴取のために出頭すべき日時・場所が記載されているので、必ず指定されたとおりに出頭しましょう。
出頭して事情を述べれば、場合によっては処分が軽減される可能性もあります。しかし、出頭しなければ刑事事件の対象とされ、逮捕されるおそれがあります。
出頭して事情聴取等の処理が終わると、その日から免許停止や免許取消しの効力が生じます。
行政処分が免除される?違反者が受けるべき講習とは
免許停止処分の対象となった場合は、講習を受けることで処分が免除されたり、免停期間が短縮されたりします。
講習を受けるかどうかは任意です。
免許取消し処分を受けた場合には、講習を受けなければ新たに免許を取得することができません。
違反者講習
基礎点数が3点以下の軽微な違反による点数が累積して6点になった人を対象とする講習で、受講すれば免許停止処分が免除されます。ただし、前歴がある場合は受講できません。
講習時間は6時間ですが、いくつかのコースがあります。手数料はコースによって異なり、9,950円~13,400円です。
停止処分者講習
免許停止処分を受けた場合で、違反者講習の対象とならない人は、停止処分者講習を受けることができます。この講習を受講すると、最後の考査の成績に応じて以下のように免停期間が短縮されます。
| 講習の種類 | 対象となる 免停期間 | 講習時間 | 手数料 | 短縮される期間 |
| 短期講習 | 39日以下 | 6時間 | 11,700円 | 20日~29日 |
| 中期講習 | 40日~89日 | 10時間(2日間) | 19,500円 | 24日~30日 |
| 長期講習 | 90日~80日 | 12時間(2日間) | 23,400円 | 35日~80日 |
取消処分者講習
免許取消し処分を受けた人が新たに免許を取得するためには、取消処分者講習を受講することが義務づけられています。
取消処分者講習は欠格期間中にも受講できます。ただし、終了証明書の有効期間は1年間なので、それまでに免許を取得できなければ改めて講習を受講しなければなりません。
講習時間は13時間(2日間)、手数料は30,550円です。
まとめ
交通事故を起こすと、事案の内容によっては違反点数が大きく加算され、免許停止や免許取消しの処分を受ける可能性があります。仕事や生活に車が必要な人にとっては、厳しい事態に陥ってしまうかもしれません。
車やバイクを運転をする際には、常に安全運転を心がけるべきでしょう。
万が一、交通事故を起こしてしまった場合には、当て逃げやひき逃げなどをせず救護措置などを適切に行うことが、違反点数を少しでも抑えることにつながります。
