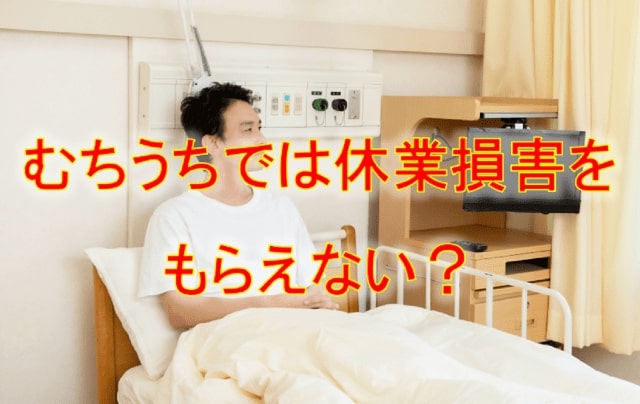
交通事故でケガをして仕事を休まなければならなくなったときは、加害者に対して休業損害を請求できます。
しかし、むちうちの場合は加害者側の保険会社から「休業損害は払えない」と主張されるケースが少なくありません。むちうちで休業損害をもらえないというのは本当なのでしょうか?
結論からいうと、むちうちで休業損害をもらえるかどうかはケースバイケースです。ただ、被害者の対応次第でもらえるはずの休業損害をもらえなくなる可能性もあります。
今回は、むちうちの休業損害で損しないためのポイントをお伝えします。
むちうちでは仕事を休めない?
そもそも休業損害は、交通事故で負ったケガの痛み苦しみやその治療のために仕事ができないと認められるときに支払われるものです。
むちうちの場合、首や肩、背中、腕などの痛みやしびれ、吐き気、めまいなどの症状が出ます。「仕事ができない」と認められるかどうかは、症状の程度や職種によって異なってきます。
建設作業などの力仕事や危険な作業に従事している場合は、仕事ができないと認められる可能性が高くなります。
一方、事務職などであまり体力を要しない仕事では、症状が軽度の場合は「仕事に支障なし」と判断される可能性もあります。
その判断を行うのは、保険会社ではなく医師です。医師が休業の必要性を認めた場合には休業損害がもらえるということになります。
したがって、交通事故でむちうちを負ったときには医師に症状と仕事にどのような支障があるのかを具体的に伝えて、休業が必要であることを診断書に記載してもらうことが大切です。
仕事優先で治療を後回しにするデメリット
交通事故でむちうちを負って休業の必要性があっても、「仕事が忙しくて休めない」「休むと周りの人に迷惑がかかる」といって仕事を優先してしまう人も少なくありません。
しかし、仕事優先で治療を後回しにすると以下のデメリットを受ける可能性があるので要注意です。
交通事故との因果関係を否定され、休業損害をもらえなくなる
交通事故に遭った後、病院を受診するまでの間に期間が空いたり、治療中でも仕事を優先させて通院の間をが空けすぎたりすると、交通事故とケガとの因果関係を証明するのが難しくなってしまいます。
その場合、保険会社から「あなたのケガは今回の交通事故と関係ないものと判断します」と主張される可能性が高くなります。交通事故と無関係のケガで仕事を休んでも、休業損害はもらえません。
交通事故で身体に痛みを感じたら、仕事が忙しくても必ずその日のうちに病院で受診し、その後も継続的に通院しましょう。
むちうちの場合は軽症でも最低月に1回、できれば2~3日に1回のペースで通院することが望ましいです。
休業損害をもらえても減額される
休業損害は、交通事故によるケガで仕事を休んで減収した場合にのみもらえます。たとえ無理をして働いた場合でも、減収がなければ休業損害はもらえません。
そのため、むちうちを負いながらも無理をして出勤すると、働いて収入を得た分だけ休業損害が減額されます。
むちうちを負っても仕事を一切休まず、減収がなかった場合は休業損害は一切もらえないことになります。
慰謝料を減額される
通院の頻度が少ない場合には治療の必要性があまり必要がないと判断され、その分精神的苦痛も軽いものとして慰謝料を減額される可能性が高くなります。
むちうちの痛み苦しみを押して働いたのに休業損害がもらえない上に慰謝料まで減らされたのでは損をする一方なので、治療を後回しにするのは禁物です。
後遺障害等級の認定で不利になる
治療を受けてもむちうちが完治しない場合には、後遺障害等級の認定を受けて後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を加害者に請求できます。
しかし、事故から受診までの期間が空いていたり、通院期間中に空白期間があると事故と負傷の因果関係を否定されて後遺障害等級に認定されない可能性があります。
また、通院頻度が少ない場合も、軽症と判断されて後遺障害等級の認定に至らないことがあります。
後遺症が残っても、後遺障害等級に認定されなければ補償もなく一生苦しみ続けなければなりません。
仕事が忙しくても適切な頻度で通院して治療を受けることは、身体のためにも損害賠償請求のためにも非常に重要であることを覚えておきましょう。
交通事故でむちうちを負ったら休業損害を申請しよう
重傷で休業の必要性が明らかな場合は保険会社の方から休業損害を受け取る手順を案内してくれますが、むちうちの場合は被害者の方から申請しなければ休業損害を支払ってもらえないこともあります。
ここでは、休業損害の申請方法や申請する際の注意点をご紹介します。
休業損害を申請できる条件
休業損害を申請するための条件は、以下の3つです。
①交通事故が原因で負傷したこと
②休業の必要性があること
③収入が減少したこと
申請する際には、この3点を証明する必要があります。①と②については医師の診断書で証明しますが、③については勤務先の会社で証明してもらう必要があります。
医師の診断書については、通常、保険会社が病院から直接取得しているので、被害者が提出する必要はありません。
休業損害を申請できる条件
休業損害を申請するには、勤務先の会社で「休業損害証明書」という書類を発行してもらい、源泉徴収票や給料明細などを添付して保険会社へ提出します。
休業損害証明書の用紙は保険会社でもらえますが、保険会社のホームページからダウンロードできるようになっているところも多く、ダウンロードしたものを使用しても構いません。
会社で休業損害証明書に記入してもらう主な事項は以下のとおりです。
・仕事を休んだ日
・休業日に給料を支払ったかどうか
・事故前3ヶ月の給料額
・会社代表者の印鑑
※自営業の方は休業損害証明書を提出する必要はありません。
事故前の収入を証明できる資料を保険会社へ提出して休業損害の支払いを求めることになります。通常は確定申告書の控えを提出します。
休職延長について
むちうちの場合、休職期間が3ヶ月を超えると保険会社は休業損害の支払いを打ち切ろうとしてくることがよくあります。一般的にむちうちが3ヶ月程度で治癒すると考えられているためです。
しかし、実際にはむちうちの治療に必要な期間はケースバイケースであり、一律に3ヶ月で休業損害を打ち切ってよいものではありません。後遺症が残るようなケースでは、すくなくとも6ヶ月の治療継続が必要でしょう。
とはいえ、治療期間の最初から最後まで一切働けないかというと、そうとも限りません。
治療継続は必要だけれど仕事に支障はなくなったという場合は休業損害が打ち切られます。ある程度は働ける状態になった場合は、休業損害が減額された上で支払われることもあります。
むちうちが治らずに休職延長を求めたい場合は、初診時と同じように医師に症状と仕事にどのような支障があるのかを具体的に伝えて、休業の必要性について判断を仰ぎましょう。
医師が休職延長の必要性を認めた場合は、保険会社へ休業損害の延長を請求できます。
まとめ
むちうちでは休業損害はもらえないと誤解している方もいらっしゃいますが、症状の程度によっては休業損害の請求が可能です。
・仕事が忙しくても通院すること
・医師に症状や仕事への支障をしっかりと伝えること
・無理して出勤しないこと
以上のことが休業損害を請求するためのポイントとなります。
仕事を優先して治療を後回しにすると、もらえるはずの休業損害をもらえなくなる可能性が高いのでご注意ください。
