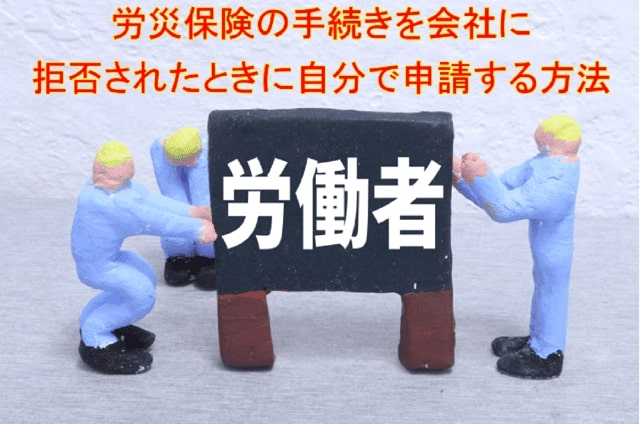
仕事中や通勤中に交通事故に遭ったときは、自動車保険だけでなく労災保険を使って補償を受けることもできます。
相手が無保険の場合や、ひき逃げなどで加害者不明の場合は労災保険が役に立つことでしょう。また、労災保険の給付金は過失相殺されないことや、休業補償を早期に受給できることなど、自動車保険にはないメリットもあります。
実際に労災保険を使おうとすると、会社が申請手続きを拒否するケースも少なくないようですが、そんなときは自分で申請することが可能です。
ここでは、会社が労災保険の手続きを拒否する理由や、自分で労災保険を申請する方法をご紹介します。
会社が労災保険の手続きを拒否する理由
労災保険を使うときは、労働者からの申し出によって会社が申請手続きを行うのが一般的です。
しかし、なかには会社が申請手続きを拒否することもあります。その理由として、以下のことが挙げられます。
労災保険料が上がるから
労災保険を使うと、会社が納付すべき労災保険料が上がる可能性があります。しかし、そのケースは限られています。次のケースでは、いくら労災保険を使っても労災保険料が上がることはありません。
・通勤中に事故が発生した場合
・常時雇用している労働者が20人未満の会社
・労災保険に加入してから3年未満の場合
その他の場合でも、労災保険を1回使ったからといって必ずしも保険料が上がるわけではありません。
労災保険料の算定には「メリット制」という制度が導入されています。簡単に言うと、過去3年間の保険料の納付額や労災を使って給付を受けた金額などに応じて、労災保険料率を増減する制度のことです。
そのため、労災保険を1回や2回使っただけでは保険料が変わらない可能性も十分にあります。
ただし、メリット制に基づいて労災保険料率を算定するのは非常に難解です。実際に保険料率が上がるかどうかを確認するには、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
労災保険を使っても保険料に影響がないケースは少なくありませんが、そのことを会社の社長や上司が知らない可能性は十分にあります。影響がない場合はその旨を労働者から説明し、労災保険の申請を依頼するとよいでしょう。
事故に対する法的責任を問われるから
会社が労災保険の手続きを拒否するのは、以下のような法的責任を問われることを恐れているからかもしれません。
・労働安全衛生法違反や業務上過失致死傷罪による刑事罰
・労働者や事故の相手方からの民事上の損害賠償請求
・労働基準監督署からの是正勧告や指導、使用停止等命令などの行政処分
会社がこれらの法的責任を回避するために労災保険の適用を避け、穏便に事態を収めたいと考える気持ちはわからなくもありません。
しかし、会社は労働災害が発生した場合には管轄の労働基準監督署長に報告しなければならないことが法律で定められています。この義務に違反したときは「労災かくし」という犯罪が成立し、会社が罰金刑の対象となってしまいます。
労働災害として突発的な交通事故が発生した場合、会社が深刻な法的責任を問われる可能性は低いはずです。特に、労働者が加害者ではなく被害者の場合はなおさらです。労災かくしをするよりも、きちんと労働基準監督署長に報告する方が得策といえるでしょう。
社長や上司が法的責任を恐れている場合は、労働者から以上のことを説明して労災保険を適用するよう依頼することになります。
企業イメージが悪化するから
近年では、労働災害の発生がメディアでもよく報道されるようになりました。悪質な労働災害が明るみに出ると企業イメージが悪化し、会社の経営に悪影響が及ぶ可能性があります。
この点も、会社が労災保険の手続きを拒否する理由となることがあります。
しかし、一般的な交通事故が発生したケースでは、企業イメージに深刻なダメージが及ぶことは考えがたいです。
また、労働災害の発生を労働基準監督署長に報告しなければ労災かくしとして会社が刑事罰の対象となることは先ほどご説明したとおりです。
したがって、やはり労働者の方から社長や上司に対して、労災保険を適用した方が得策であることを説明すべきということになるでしょう。
会社の了承なしに労災申請はできないのか
結論から言いますと、会社の了承がなくても労働者が自分で労災申請をすることも可能です。以下で、その理由をご説明します。
労災保険の申請者は労働者自身
そもそも誰が労災保険を申請すべきかと言いますと、労働者自身(またはそのご遺族等)です。会社ではありません。言い換えれば、労災保険を申請することは労働者の権利であって、会社の了承など必要ないのです。
通常は会社が申請手続きを行いますが、それは便宜上、労働者が行うべき手続きを会社が代行しているにすぎません。
申請書の事業主証明欄は空欄でも可
労災保険の申請書には、負傷の発生時期、災害の原因や発生状況などを事業主が証明する旨を記載する欄があります。
この事業主証明欄への記載を会社に拒まれた場合は労災申請ができないと考える方が多いですが、そんなことはありません。
発生した事故が労働災害に該当するかどうかは労働基準監督署が判断することであり、事業主の記載の有無によって左右されるものではないからです。
申請書の事業主証明欄が空欄のままでも労働基準監督署で申請を受理してもらう方法については、後ほどご説明します。
会社には労災申請を了承する義務がある
会社は労働災害が発生した場合には労働基準監督署長に報告しなければならないこと、労災かくしをすると犯罪に該当することは既にご説明しました。
さらに、会社は労働者から労災給付を受けるために必要な証明を求められたときには、速やかに証明しなければならないという義務も法律で定められています。
つまり、労働災害が発生して労働者が労災給付を求めている以上、会社が労災申請を拒む理由はなく、了承する義務があるのです。
会社とのトラブルを避けるためにも、できれば会社の了承を得て申請してもらいたいところです。ご自身で申請する前に、一度は会社と話し合う意味はあるでしょう。
話し合いが進まない場合は、弁護士に間に入ってもらうことで会社の了承が得られる可能性もあります。
自分で労災保険の申請をする方法
会社が労災申請を頑なに拒み、話し合いの余地がない場合はご自身で労災申請をした方が早く保険給付が受けられるでしょう。
ここでは、ご自身で労災保険の申請をする方法をご紹介します。
申請書を入手する
労災保険の申請書の書式は、最寄りの労働基準監督署で入手できます。また、厚生労働省のホームページからダウンロードしたものも使用できます。
厚生労働省|労災保険給付関係請求書等ダウンロード
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
申請書に記入する
申請書の書式を入手したら、必要事項を記入します。上記の厚生労働省のページから記載例もダウンロードできますので、参考にしつつ記入すれば特に難しいところはありません。
事業主証明欄については、会社が記載を拒む場合は空欄のままで構いません。
報告書を作成する
事業主証明欄を空欄にしたまま申請書を提出する場合は、報告書を別途作成して労働基準監督署へ提出するのが一般的です。
この報告書には、会社に事業主証明欄への記載を求めたにもかかわらず拒まれた経緯を記載します。
様式や書き方に特段の決まりはありませんので、会社に拒否された顛末が具体的に記載されていれば受理されるはずです。不安なときは、労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。
労働基準監督署へ書類を提出する
以上の書類がそろったら、勤務先を管轄する労働基準監督署へ提出して申請します。
申請が受理されたら、事故と負傷が労働災害に該当するかどうかなどについて、労働基準監督署による調査が行われます。聴き取り調査が基本ですが、交通事故証明書や診断書、その他の資料の提出を求められる場合もあります。
ケースによっては、事故と業務や通勤との関連性の立証が難しいこともあるかもしれません。困ったときは、弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
仕事中や通勤中に遭遇した交通事故が労働災害に該当する限り、労災保険を申請するのは労働者の権利です。会社が拒否する場合には、ご自身で労災申請をして適切な補償を受けるようにしましょう。
ただ、労災の申請をめぐって会社とトラブルになるのも避けたいところでしょう。弁護士に間に入ってもらうことで円満な解決も期待できるので、まずは弁護士に相談してみるのもお勧めです。
