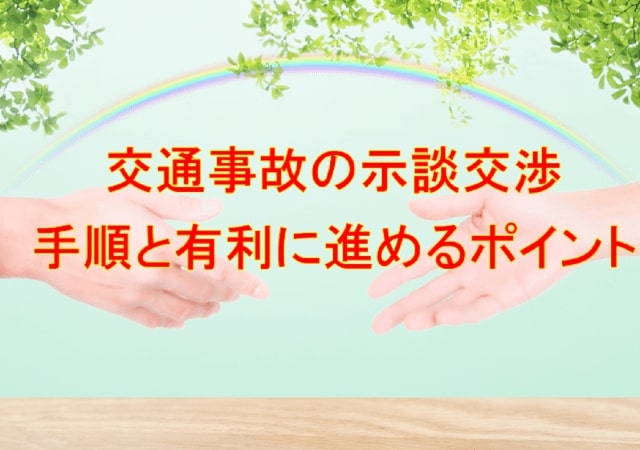
交通事故の示談交渉ってなに!?
交通事故の被害者が加害者に対し賠償金を請求するための話し合いです。
交通事故の示談交渉で重要になるものが書類です。
口頭での証言のみではトラブルの引き金となるので、可能な限り必要書類を集めましょう。
物損事故の場合
①交通事故証明書 ②修理の見積書 ③事故車両の写真
人身事故の場合
①交通事故証明書 ②事故発生状況報告書 ③診療報酬明細書 ④診断書 ⑤源泉徴収票 ⑥確定申告書の控え ⑦給与明細書 ⑧各種領収書 ⑨後遺障害診断書 ⑩休業損害証明書
これらの書類の内容をふまえて示談交渉は進められ、賠償金が提示されます。
交通事故の示談交渉に必要な書類
ここでは頻度の多い、人身事故についての書類の集め方について解説します。
交通事故証明書
交通事故にあった場合、まずは加害者の身元確認のため、免許証、健康尾保険証などをカメラで撮影したり、連絡先や氏名をメモをとったり名刺があれば貰うようにしましょう。
次に、必ず警察に通報して交通事故証明書を発行してもらいましょう。
交通事故証明書は警察が現場検証をしてから発行されます。
もし加害者が「警察を呼ばないでほしい」「お金を払うから示談してほしい」と言ってその場で金銭のやり取りをしてしまうと、のちに正しい手続きでの示談をすることが出来なくなる可能性があります。
第三者に介入してもらことで、余計なトラブルを防ぎ示談交渉もスムーズになるので、交通事故に遭ったらまずは警察に通報しましょう。
事故発生状況報告書
事故発生状況報告書は、交通事故が、起きた状況を詳しく書いた書類です。
この書類は保険金などを受け取るために必要な書類となり、被害者が作成します。
保険会社に記入用紙と記入例の用紙を送付してもらい、分かる範囲で記入して下さい。
診療報酬明細書
診療報酬明細書は、被害者が受けた治療費の明細書です。被害者が加害者側の保険会社に掛かった分の治療費を請求するために必要な書類です。加害者側の保険会社が保管しています。
保険会社に問い合わせをして、コピーを送付してもらいましょう。
診断書
診断書は、病院でもらうか保険会社が保管しています。
病院でもらえない場合は、保険会社に問い合わせをして、コピーを送付してもらいましょう。
源泉徴収票
会社員の方は、会社に発行してもらいましょう。
個人事業主の方は、確定申告書を用意して下さい。
確定申告書の控え
会社員の方で、昨年度の確定申告書の控えがない場合は、会社に問い合わせをして下さい。
個人事業主の方は、昨年度の確定申告書のコピーを用意して下さい。
給与明細書
毎月の給料が分かるものを用意して下さい。通帳に記載があればそれでも大丈夫です。
各種領収書
・交通事故によって壊れた車の修理代や車の購入費用
・治療に通う際使ったタクシー代や、バス代などの交通費
・湿布や鎮痛剤を購入した際のレシートなど
交通事故の被害によって生じた費用に対して支払いをした領収書は必ずなくさないようにして下さい。
後遺障害診断書
後遺障害診断書は医師が作成してくれます。
交通事故のケガや、むちうちを負ってから、6か月が経過しても症状が改善されない場合に後遺障害の申請ができます。
後遺障害は、治療から6カ月が経過し、治療を続けてもこれ以上改善の見込みがない場合に診断されます。後遺障害診断書を作成すると治療は中止されるので、治療の継続を希望される方は、後遺障害診断書の作成は待ってもらいましょう。
休業損害証明書
会社員の方は、会社で作成をしてもらいましょう。
個人事業主の方も、休業損害の申請か可能ですが手続きが少し複雑です。
休業損害証明書の代わりに、休業した事実を証明するものや、減収した金額がわかるもの、交通事故前の収入が分かるものなど必要な書類を集めて計算することになります。
交通事故の示談交渉の流れ
物損事故の示談
物損事故の場合には、車の修理などがすべて終わり、損害額が確定した時点で示談交渉を開始します。
物の損害だけなので、損害額が確定しやすく、交通事故から1ヶ月くらいで示談交渉ができることが多いです。
人身事故の示談
人身事故の場合には、治療が終了してから示談交渉を開始します。
治療が長期になることが多く、交通事故から半年から1年近く経ってから示談交渉が開始されることが多いです。
人身事故の示談交渉が長引く理由
治療を終了する時期はケガの状態により様々です。状態により治りが悪いケガもあります。
なかなか症状が改善されないからといって永遠に治療を続けていくことは出来ません。
そこで症状固定といって医師が、症状はあるけどこれ以上治療をしても治る見込みがないと判断することがあります。
この判断は医師の見解によって異なってきますが、大体は6か月から1年の間にされると言われています。
死亡事故の示談
死亡事故の場合は、葬儀などが終わってから損害額を確定します。すぐに示談交渉をすることができますが、実際には、49日の法要が終わった頃に示談交渉を開始することが多いようです。
交通事故の示談の期間はどれぐらい?
個々のケースによってかかる期間は変わってきます。
・損害額のみの示談期間………3か月以内に示談がまとまるとが多い
・過失割合に争いのある示談期間………3か月以上かかることも多く、裁判に移行することもある
・後遺障害等級の争いがある示談期間………6か月~1年以上かかることもある
争いを少なくし、交渉期間を少しでも短くするためには、交通事故に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、弁護士費用がかかることなく複雑な手続きを弁護士が変わって行ってくれます。
弁護士費用特約のみを使う場合は、翌年の等級に影響することがないので保険料が上がる心配もありません。
交通事故の示談交渉と裁判の違い
交通事故の示談交渉では、相手(保険会社)と補償について話し合いによって合意に至ります。
これに対し、合意に至らなかった場合に裁判が行われます。裁判の場合はお互いの主張を立証し裁判官が法律的に妥当な主張を採用しそれにもとづいて判決がされます。
判決では、こちらの主張が必ずしも認められるとは限らないので負けてしまうこともあります。
個人で行う示談交渉のメリットとデメリット
示談交渉のメリット…被害者が自分自身で対応できるので、特に費用はかかりません。示談内容によって早期に決着することもできます。
示談交渉のデメリット…交通事故に対する知識がない場合、加害者側の保険会社のいいなりになり損をする可能性があります。加害者側の保険会社は低額な任意保険基準で損害賠償金額を計算してくるので、示談金はかなり低くなります。
交通事故の示談金を左右する要素
後遺障害等級の認定
後遺障害認定とは、交通事故によるケガがこれ以上治療を継続しても完治せずに残ると判断された障害のことです。
後遺障害の認定には医師の診断書が必要となります。後遺障害認定には、1級~14級までの等級があり、それぞれの等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益を相手に請求することができます。
過失割合
過失割合とは、交通事故が起きた時にどちらに過失が多くあるかを割合で示すものです。
自分の過失が小さい方が受け取る示談金は増えます。
弁護士基準
弁護士基準とは、交通事故の損害賠償金の計算方法の1つです。
交通事故の損害賠償金の計算方法には、自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準の3種類があります。
この中で、自賠責基準が最も安く、弁護士基準が最も高額になります。
同じようなケースの交通事故でも、弁護士基準で損害賠償金額を計算すると、他の2つの基準で計算した場合と比べて示談金の金額が2倍以上になることがあります。
損害賠償金の請求権には時効がある
時効の期間
損害賠償請求権の時効期間は、民法において、損害及び加害者を知ったときからものによって違いますが3年~5年の時効があると規定されています(民法724条)。
よって、示談交渉を円滑に進めていく必要があります。
まとめ
めったに起こることのない交通事故。なかなか専門的な知識を持っている人は少ないでしょう。
示談交渉は自分で行うことも出来ますがかなりの時間と労力を必要とします。スムーズに進めていくためには専門家である弁護士に依頼するのも良いでしょう。
「弁護士に依頼するのはおおごと!」と思ってしまう方もいるかもしれませんが、最近では弁護士を使う方も珍しくありません。トラブルが一切ない場合でも書類の作成など煩わしいことを本人に代わって手続きしてくれるので便利です。
鍼灸整骨院かまたきでは、交通事故に強い弁護士を紹介することができます。どうするか悩んでいる方は相談にものりますのでお声がけください。
